|
|
|
 実力を付けてきている海外勢を受けて立つために、今年から本部特別練成会(特練会)が始まりました。
実力を付けてきている海外勢を受けて立つために、今年から本部特別練成会(特練会)が始まりました。
|
|

 4月は特練会と講習会で多忙でした。
4月は特練会と講習会で多忙でした。
今年から始まった特練会は毎回横浜で開催されていましたが、4月13日は四国の高松市で行われ、高松のみならず、大阪、奈良、京都、山口、福岡、近県では徳島、高知、愛媛等々、スポチャン大好き人間が集まってきました。
この高松での特練会では大きな収穫がありました。四国勢は特に基本動作に力を入れていて、昨年、世界チャンピオンの野村五月選手(高知県)や日本代表の川田多美子選手(香川県)、その他の選手も全員が日本代表になれる位の大変に高いレベルで、昨年の世界代表クラスの選手を無名の選手が破ったり、また誰が出てきても僅差の判定となり、常に旗が割れていました。打突の試合では大阪の富田林の選手が目立っていました。
そのような新しい力が台頭してくる事が大変嬉しいことですね。その他の地区も余程練習方法を考えないと、全日本選手権では来年はおろか、今年も良い結果につながるのはなかなか難しいかもしれませんね。
この様に四国勢が伸びてきた理由は、スポチャン人口に関わらず指導者の卓越した指導力があると思われます。私は常々、指導という事があるとするならば(指導はしなくても良いのだが。自分で自発的に開発するものだから=自己開発)ワンポイントアドバイス位が丁度であろうと考えています。指導とか育成などと大上段に構えると、手・つま先から頭の天辺まで、全て意に叶わなければ済まない様なオーバーティーチングが日本の教育の中に存在しているようですが、それらがマニュアル人間を作る、所謂ゆとりのない教育と言われる所以なのでしょう。
それを解決するには「百聞は一見にしかず」のことわざ通り、武者修行、即ち日本選手権や世界選手権、ヨーロッパ選手権、アジア選手権等で、世界の一流を見ることでしょう。何か自分で感じ取る事が必要なのです。 口でいかに説明を労してもできなかった事が解決できるかもしれませんし、それは選手・指導者共々自信に繋がり、功を奏するかもしれません。
"Next
The Top of the World"
|
|



 特練会を通して普段と違う指導を受けるのも、選手にも先生方にとっても良いことなのですね。新しいものを掴むチャンスかもしれません。
特練会を通して普段と違う指導を受けるのも、選手にも先生方にとっても良いことなのですね。新しいものを掴むチャンスかもしれません。
|
|

 そうですね。
そうですね。
この様な高松での特練会の後は鹿児島県での通常の講習会がありました。こちらは参加者が鹿児島県内からでチビッ子が多かったですね。先生には本部で修行していた井川君や柿原君がいましたので技術的には不足はありません。彼らの指導の元、この子供達の将来が楽しみですね。
特練会は自分稽古ですから強くなります。今のところ月に1度のペースで行われていますが、本当はもっと数多く、せめて週に1回くらいの頻度でやれば目に見えた効果が出てくるでとは思います。しかし特練会の他にも各自が各道場で練習しているわけですから、まぁ現時点では充分でしょう。
|
|



 ところで、今年のヨーロッパ選手権大会は如何でしたでしょうか?
ところで、今年のヨーロッパ選手権大会は如何でしたでしょうか?
|

 5月3日に、エストニアのタリンで開催されました第5回ヨーロッパ大会で特に目立っていたのは、基本動作でのOlga Bobrova選手(オルガ選手 エストニア)でした。動きが大変美しい。この選手は、昨年の世界大会基本動作1,2級の部で3位でしたが、今年はもっと上位で活躍するでしょうね。
5月3日に、エストニアのタリンで開催されました第5回ヨーロッパ大会で特に目立っていたのは、基本動作でのOlga Bobrova選手(オルガ選手 エストニア)でした。動きが大変美しい。この選手は、昨年の世界大会基本動作1,2級の部で3位でしたが、今年はもっと上位で活躍するでしょうね。
 第33回世界大会 オルガ選手(エストニア)の姿勢
第33回世界大会 オルガ選手(エストニア)の姿勢
打突部門では、ヨーロッパ勢は押し並べて一皮も二皮も洗練されてきました。特に、昨年の世界大会、団体戦打突部門優勝のイタリア、2位のフランスがやはり強い。ロシアは打突部門より基本動作の方が若干強い感がありますね。そして何よりヨーロッパ勢は練習量が多いようです。それは動きを見ていれば判ります。
日本選手がヨーロッパ人に対抗するにはスポチャンの原点に戻れば良い。スポチャンはスピードとタイミングの祭典ですから、体格などは関係ないのです。その点、近年台頭してきた大阪や関東の中学生・高校生の若い選手が実力を上げているのは、その動きの軽さとスピードです。今年の世界大会ではヨーロッパ勢とも相当に戦えるのではないかと期待しています。
またそうなると、ヨーロッパの指導者は彼らの早さに対応できる指導をし始める。そのようにお互いに切磋琢磨して、どんどんレベルが上がっていけば良いわけのですね。今後の成長ぶりが楽しみです。
|
|



 有り難うございました。
有り難うございました。
国内の若い選手もどんどん育って来ているのですね。素晴らしいです!
さぁ、今月末には少年少女選手権大会です!参加選手の皆さん、いつもの実力が発揮できますよう、頑張って下さい!!
次回のインタビューもお楽しみに!!
|

 
|
また、会長にお聞きしたい事があれば[ メールマガジン、お問合わせページ ]からお送り下さい!
|
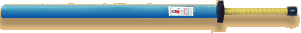
|
 |